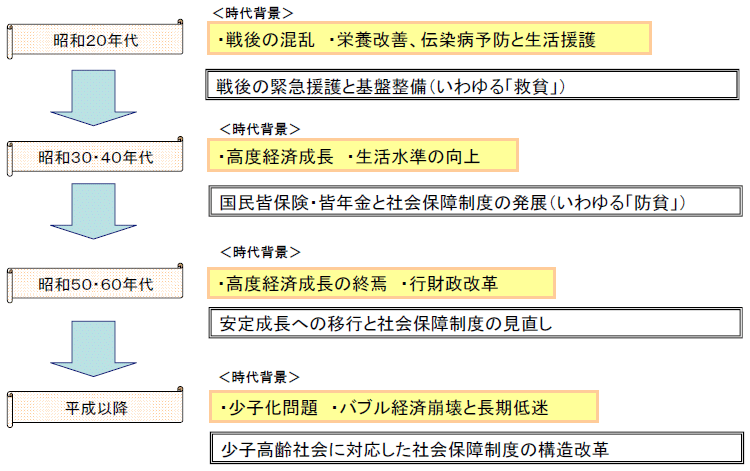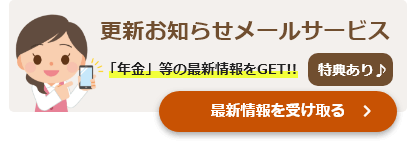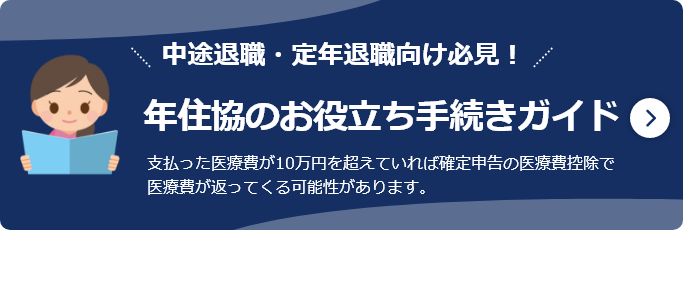年金を若者にどう伝えるか

公的年金制度は、個人の生活にとどまらず、社会の安定にとっても必要不可欠である。そのことをどう伝えればよいか。若者の保険料未納や将来不安が語られる都度考えさせられてきた。
以下、私自身のこれまでの人生のなかで考えてきたことや、教室やメディアで学生や社会人と向き合い語り合った経験を踏まえて、ポイントだと思うことを書き留めておきたい。
家族扶養から社会的扶養へ:年金・社会保障の成果
皆保険・皆年金の実現は1961年4月。筆者の高校入学時であった。前年には、安保の騒動を経て、池田内閣が誕生し、国民所得倍増計画が策定された。10年後には月給が2倍になるとか、福祉国家の建設など、夢のような話が子どもの耳にも入ってきた。その皆保険・皆年金はどういう意味をもったのか。私自身の家族史の振り返りを通して考えてみたい。
当時のわが家は三世代同居、8人家族の兼業農家。父が会社勤め、祖父が農業、母は家事の傍ら農業の手伝い。祖母は家事のほか、孫の世話、それに留守番役であった。
郷里は広島市近郊。私の小学校入学時は「村」であった。農地はもともと小作地であったものを、戦後の農地解放で手にした。家族の食をぎりぎり自給できる程度の零細農家ではあったが、それでも人手のみの農業であったから、農繁期はけっこう多忙であった。
これは、私の世代の地方出身にみられる、幼少期の典型的な家族像である。付言すれば、祖父母は大正に入るとともにハワイに出稼ぎ移民し、関東大震災の年に帰国した。震災直後のため横浜には入港できず、清水港から上陸した。そういうわけで、父親もハワイ育ちで、小学校もハワイで卒業した。父母はともに被爆者であったが、幸いにも原爆症を患うことはなかった。とは言っても、昭和30年代初頭、結核が国民病と言われた時代で、軽症ではあったが、父母それに私も結核で療養した。
私が最初に耳にした年金は「福祉年金」。昭和34年に国民年金法が制定され、その秋から福祉年金の支給が始まった。しかし、扶養義務者である父の所得による制限により、祖父母は対象外であった。わずか月額1,000円の「あめ玉年金」ではあったが、近所の多くの年寄りが手にする年金を祖父母は欲しがった。祖父母には現金収入が一切なく、通院するにも一家の財布を管理する母に気兼ねしていた。ちなみに、当時の健保家族の自己負担は5割、発足当初の国保も同様であった。皆保険を実現したとはいうものの、10割給付であった健保本人以外は所得と受診率の間に明瞭な正の相関関係がみられた。
いずれにしても、経済的には父が祖父母を扶養し、終末は母が自宅で世話をして看取った。その代わり、家屋敷と田畑はすべて長男である父が相続した。父母の老後は、祖父母とは打って変わり、子どもたちから完全に自立したものであった。同居による嫁の苦労を経験した母は、最後まで子との同居を望まなかった。それを可能にしたのは父母の年金であり、老人医療であり、介護保険であった。それでも近隣にいた長男、次男夫婦とはスープの冷めない距離で、良好な親子関係を保っていた。
母は、国民年金に発足当初から加入していた。再軍備のための資金調達などという今では信じられない反対運動があり、しかも任意加入する主婦は少なかった時代にあって、よく加入していたものだと思うが、「老後は子供たちに迷惑をかけたくない」とはよく言っていた。それと、農村地帯でもあり保険料の納付組織として婦人会が機能していたことも、納付漏れを防いでいたのだろう。さらに、繰上げ受給が多かった当時にあって、65歳まで待って受給開始したことにも感心している。母にとって、年金は小遣いではなく、父の年金とともに生活の支えにするものだったからであろう。
父親が退職し、年金を受給開始するのと、私の就職はほぼ同時期であった。年金をはじめとする社会保障がなければ、相続を前提に長兄が両親の扶養をするか、4人兄弟で負担を分担することになったはずである。その負担を免れた反面、税や社会保険料を負担している自分に納得した。
このような家族史と社会保障の係わりは、私の世代ではごくありふれたものである。高齢世代に関する限り、わが国は十分に福祉国家を実現したと評価できるように思う。今後の課題は、そのことをきちんと評価した上で、子ども・子育て支援の充実など、必要な見直しを行い、将来に繋げることだ。
図1 社会保障制度の変遷