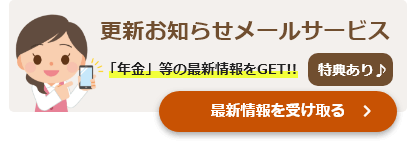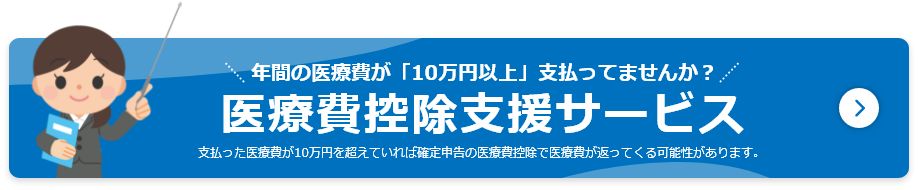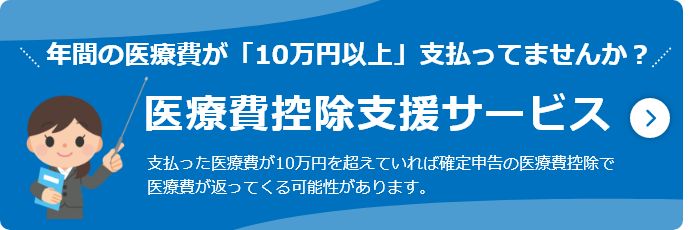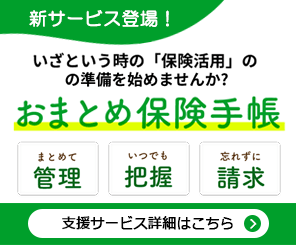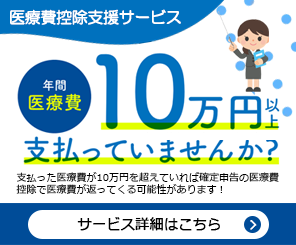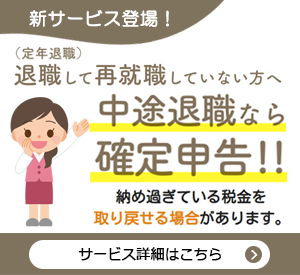被用者年金一元化をめぐって

昨年は、公的年金制度の歴史上、大きな節目になる年であった。一つは、マクロ経済スライドの施行により、年金制度の持続可能性の確保に向けた平成16年改正のフレームが動きだしたこと。もう一つは、昨年10月の被用者年金一元化法の施行により、昭和59年の閣議決定による公的年金制度の一元化が実現したことである。
被用者年金一元化については、これが公的年金制度改革の「最終的な到達点」なのか、それとも長い道程の「一里塚」にすぎないのか、いろいろな見方があろう。たとえば、民主党が提案しているような、税財源による最低保障年金とセットにした単一の所得比例年金への一元化のような姿を最終到達点だと考える人には、一里塚にすぎないのかも知れない。が、ここに至る長い過程を見聞してきた私には、相当に完成度の高い到達点であるように思える。
この間の経緯を振り返りつつ、雑感を記しておきたい。
なぜ一元化か?
昭和36年に実現した皆年金は、被用者年金の適用外にあった自営業者等を対象とする国民年金を創設することにより達成したもので、制度分立を前提した皆年金体制であった。しかし、この体制の下では、産業構造・就業構造の変化に伴って、制度間の給付と負担の不均衡(格差)の発生が避けられず、公的年金制度として求められる世代間扶養の機能をはたし得ない。
年金制度の成熟化の過程で、財政が賦課方式への傾斜を強めるなかで、この問題が顕在化するようになり、昭和50年代に入って、「制度間の給付と負担の公平性」や「財政の安定性・持続可能性」の確保が政策課題になった。目指したものは、制度間調整による同一給付・同一負担の実現とか、保険集団の規模拡大・保険者間の財政の共同化によるリスク分散機能の強化であり、それらを括って「一元化」という政策課題で論じられるようになった。
昭和50年代には、老人医療費が急増し、国保財政が悪化するなかで、医療保険制度改革を巡っても、制度間調整がテーマになり、ときには一元化論にまで発展することになった。しかし、医療と年金の間には決定的な違いがある。医療では、医療提供体制の影響を強く受けるほか、保険者機能の働く余地が相当にあり、表面上の均衡論では論じられないことである。その意味では、年金の方が議論の整理はしやすいのかも知れない。しかしその一方で、医療が短期的な収支の均衡論で論じることができるのに対して、年金は長い過去を背負い、また将来的にも不確実な見通しのなかで長期的な収支の均衡を論じなければならないという難しさがある。