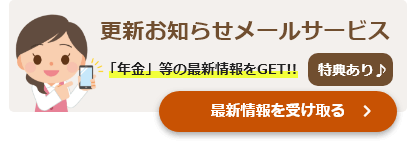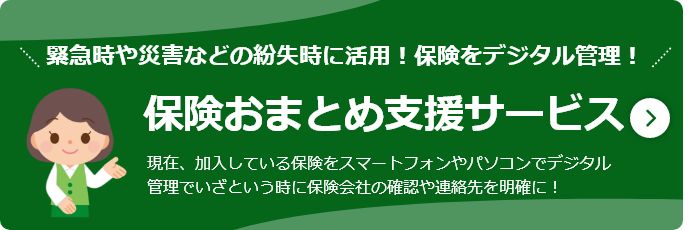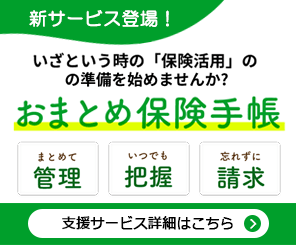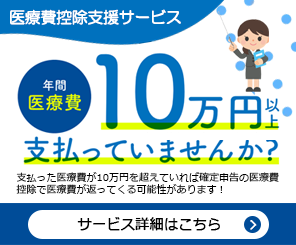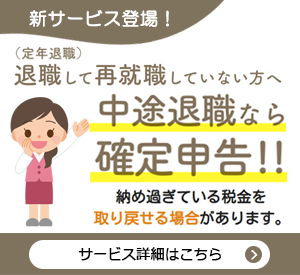受給年齢の選択を考える

給付改善策としての受給年齢の繰下げ
最近、年金の受給年齢が話題になることが多い。たとえば、平成28年10月、自民党の2020年以降の経済財政構想小委員会(茂木敏充委員長)は、「人生100年時代の社会保障へ」というとりまとめのなかで、人生100年型年金の構築に向けて、その柱として受給開始年齢の柔軟化を提案している。健康寿命の延伸に対応して高齢者の就労インセンティブを拡大すべく、「高齢者が70歳以降働く場合、70歳以降も厚生年金の保険料を納め、年金支給の繰下げを認めることで、高齢者が長く働けば働くほど年金が増える仕組みを整備すべきである。また、在職老齢年金は廃止を含めて検討すべきである」というものである。
また、平成29年10月2日、内閣府「高齢社会対策の基本的考え方等に関する検討会」(清家篤・慶応義塾大学教授)は、報告書(骨子)において、「年金受給を70歳まで繰下げることにより最大で42%増の額を受けとることができる現行制度の利用率が低いという現状がある。就業促進の観点からも十分な周知が望まれる。また、高齢期にも高い就業意欲が見られる現況を踏まえれば、繰下げを70歳以降も可能とするなど、より使いやすい制度とするための検討を行ってはどうか」と提言している。
ここで注目すべきは、かつてはもっぱら年金の財政対策として議論された「支給開始年齢の引上げ」に代わって、今は高齢者の就業促進とともに、受給権者の主体的な選択による給付水準の改善策として「受給年齢の繰下げ」が議論されていることである。
背景にあるのは、平成16年改正により導入された、おおむね100年の財政均衡期間において収支の均衡を図る有限均衡方式の下での、保険料上限固定・マクロ経済スライド・給付水準下限設定である。この改正により、与えられた収入の総額の範囲で収支の均衡を図るべく、給付水準の調整を行う一方、65歳の基準年齢での所得代替率50%という下限を設定し、次の財政検証までの間に所得代替率が下限を下回ると見込まれる場合には、給付と負担の在り方について検討し、所要の措置を講ずることとされている。
平成26年財政検証では、当面、検討を要する状況にはないと判断された。しかし、将来に向かっては、想定された8つの経済前提のうち、3つのケースでは下限を確保できない。また、下限を確保できる5つのケースにおいても51.0~50.6%で辛うじて確保できるにすぎず、しかも基礎年金の水準が著しく低下するという問題が明らかになった。
そういう問題が見えてくるなかで、財政検証では初めての試みとして、社会保障制度改革国民会議報告書が掲げた検討事項に沿った制度改正を行った場合の財政効果について、オプション試算が行われた。その結果、「デフレ下でのマクロ経済スライドの実施」、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」、「基礎年金の拠出期間の延長(65歳までの45年)」、「65歳以降での退職・繰下げ受給」のいずれもが給付水準の低下を補い、制度の持続可能性を高める上で、かなりの財政効果を持つことが確認された。
受給年齢の繰下げは、これらの包括的な政策課題のなかで位置づけられているもので、それだけ切り離して論じられているものではない。が、仮に70歳まで繰下げると、それだけで42%の増額になり、所得代替率でみても50%が71%へ引上げられるほどの財政効果がある。しかも、71%の所得代替率は、被用者年金一元化を前提にした平成26年度の所得代替率62.7%を大きく上回る。
現実の政策課題として繰下げ受給を推進する上では、65歳定年制の普及や65歳代後半に向けての雇用の拡大が課題になる。幸い、被用者については、継続雇用が中心とはいえ65歳までの雇用確保の体制が整った。また、わが国は、高齢者の就業意欲が高く、労働力率や実質的引退年齢は、先進諸国のなかで最も高いグループに属する。長い寿命、著しい高齢化の進展、生産年齢人口の減少などを併せて考えると、繰下げ受給の推進は現実的な政策の方向性として考えられよう。
いずれにしても、給付水準の抑制が進む中で、制度改正を待たずとも、個人の主体的な選択による給付改善の途があることは大いに議論されてよい。